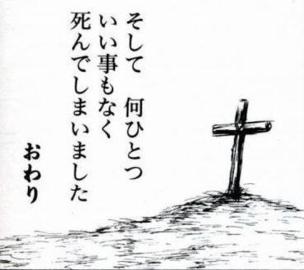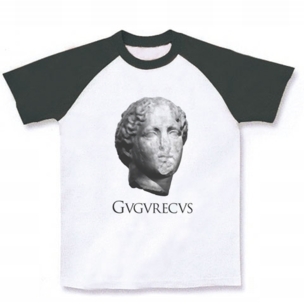>>78 それには、穀物を食べ始めてから現在までの年月が関係している。
ヨーロッパでは約1万2千年前に農耕が始まったが、日本において農耕が行われるようになったのは
稲作が伝来した弥生時代に入ってからなので、せいぜい3千年ほど前に過ぎない。
つまり、欧米人の方が農耕(=穀物食)の歴史が1万年近く長いため、より高糖質食に適応しており、
インスリン分泌能(膵臓のキャパ)が高い。
そのため、糖質を摂取するとインスリンがドバドバ出るので肥満しやすい反面、インスリン作用で
血糖値は正常に保たれるので糖尿病にはなり難い。
欧米人は、かなり顕著な肥満にならないと糖尿病は発症しない。
一方、日本人は、欧米人に比べるとインスリンがあまり出ないので、白米のような精製炭水化物や
根菜類を中心とする高糖質食でも肥満になり難い。
その代わり、糖質摂取の度に急上昇する血糖値を下げるためには、インスリン分泌能に余裕の無い膵臓が
フル稼働しなければならなくなるので、その疲弊からβ細胞が死滅して行き、糖尿病になりやすい。
人類は、農耕を始めて糖質摂取が増えてから、それに適応するためにインスリンの産生と
インスリン感受性を高めるように進化している途中にあるが、先に述べたように、人種による
「農耕を始めてからの期間」の差によって適応の度合いが異なる。
一般的なイメージとは逆に、膵臓の機能的には欧米人の方がより農耕民族として進化・適応しており、
日本人の方は肉食主体だった狩猟採集時代の名残がまだ強い。
返信する